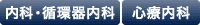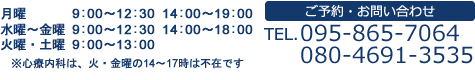始めての夏
今年も8月がやってきました。この暑い季節になると毎年必ず思い出す患者さんがおられます。あの夏から早いもので四半世紀も過ぎてしまいました。
彼女が、当時僕が勤めていた大学病院に入院してきたのは平成4年の初夏のことでした。
僕は医者になってまだ2-3ヶ月の研修医でした。彼女の病名は原発性肺高血圧という、いわゆる難病であり、これは心臓から肺動脈への血圧が高くなり、肺での酸素交換が不十分となり、呼吸困難および心不全をきたす原因不明の病気です。今なら持続点滴薬で肺動脈を特異的に拡張し肺動脈圧を正常化したり、場合によっては心肺同時移植の適応疾患ですが、当時は酸素を吸入して安静にするといった程度の治療しかなく、今考えると彼女の場合も治療というよりターミナルケアに近い入院だったのかもしれません。
彼女は僕より2歳年上でしたから、まだ二十代でした。循環器の病棟は高齢患者さんが多く、彼女はそれだけでも目立った存在でした。その上彼女は明るく、さらにとびぬけてきれいな人でした。病気の影響もあるかもしれませんが、皮膚の色がぬけるように白く、瞳は褐色というよりはすごくうすい茶色でした。担当医は3学年先輩の先生で、僕は彼女が入院してる大部屋の、となりのベッドの心臓弁膜症のおばあちゃんの担当だったので、ときどき話をするようになりました。
彼女は僕と同じで大の巨人ファンでした。その一点で僕らはすっかり意気投合し、巨人が勝った翌日には朝からジュースで乾杯が定番になっていました。ちなみに僕の担当のおばあちゃんはタイガースファンでしたが、やはり彼女と仲良くなり、この乾杯にもなぜか参加していました。
彼女の病状は徐々にですが確実に悪化していきました。最初のころは夕食後に談話室で巨人戦のナイター中継を見たり、酸素持参で自宅に外泊できてましたが、お盆過ぎごろには立ち上がるだけで息切れがひどくなり、夜中も呼吸困難がおこるようになり、個室に移ることになりました。当時(今は違います)、大学病院で大部屋の患者さんが個室に移されるということは、集中治療がしやすいと言う目的の他に、最後のお見送りのためという隠れた意味があるのを医者になりたての僕は当然知るよしもありませんでした。
個室に移ってからも僕は暇さえあれば彼女の病室に立ち寄っていました。当然、ご両親や彼女のお姉さんともすっかり顔なじみになりました。ちょうどそのころ医局の人事異動があり、彼女の担当の先生が他の病院に移られるとのことでしたので、病棟医長の先生に僕を担当にと立候補してみましたが、あっさり却下されました。後で考えると、この判断はすごく賢明で、当時の僕に彼女の冷静な治療は無理だったでしょう。このころ、僕と彼女が仲良くしているのをよく看護師さんや同僚研修医たちから冷やかされましたが、全く平気でした。
あのころの感情は今振り返ってもよく整理できません。恋愛感情ではなかったと思いますし、もちろん同情でもありません。医者になりたてで重病の人を救いたいとかの立派な使命感でもないですし、あえていうならとても気の合う仲間がたまたま身近に入院していたとの感じでしょうか。もちろん研修医とはいえ、彼女の病気の重大性、命が危機にさらされていることは僕も十分理解していましたし、彼女のご家族も、さらに残念なことに彼女自身も気づいていました。
僕は医者のくせに彼女と病気のことはほとんど話していませんでした。野球のことや、好きな音楽のこと、仕事のこと、学生時代の話や、将来のたわいのないことを話していました。彼女は僕のことを“先生は先生らしくないね”と、よく言っていました。意味を聞いたら、“よくも悪くも先生っぽくないよ”と、はぐらかされました。退院後の話もよくしていました。その年の巨人軍は優勝争い中で、優勝したら日本シリーズを見に行きたいと、茶色の瞳を輝かせていました。退院祝いは僕の懐具合を考えて、焼き鳥で生ビールに決まっていました。
うだるように暑い8月下旬のその日は朝から状態が悪くなっていました。酸素の投与量を増やしても血中酸素濃度は上昇せず、血圧は下がり、頻脈となっていました。徐々に意識レベルも低下し、病棟中も緊迫した雰囲気に包まれていました。僕はおたおたするばかりで、個室に入る勇気もなく、これっぽっちも役にもたたず、何の力にもなれませんでした。
夕方にようやく少しもちなおし、話しができました。僕が“大丈夫?”と、まったく気の利かない問いかけをすると、彼女は閉じていたまぶたを開けて“うん、先生、今まで有難う。”と苦しそうに小さな声で答えました。僕は“安くておいしい焼き鳥見つけたから、来週ぐらいどう?”と、言ったつもりでしたが、声がつまって意味不明だったと思います。彼女は声はあげなかったけど笑ってました。ほんとうに今までみたことがないくらい素敵な笑顔でした。
その後、最後の数時間を彼女はご家族とすごし、翌日の朝日が昇るころ、御家族に看取られ、ひとりで天国に旅たちました。僕は相も変わらず何もできずに医局の机に突っ伏していました。
病院地下の霊安室で僕は最後のお別れをしました。別れ際、彼女のお姉さんから声をかけられました。
“先生、お世話になりました。家族一同、感謝しております。昨晩、あのこから先生に伝言してくれって頼まれましたので、筆記しております。聞いてください”といって、メモを僕に読んでくれました。
“先生、有難うございました。本当はお手紙ちゃんと書くつもりだったのですが、急にこんなになっちゃって、もう書けそうにないんで、お姉ちゃんに伝言たのみます。苦しくて辛い入院でしたがおかげさまで楽しく過ごすことができました。いい意味でけっしてお医者さんらしくない先生に本当によくしてもらって心から感謝してます。時々、自分が病気で入院してるってこと忘れるぐらいでした。焼き鳥、楽しみにしていましたが行けなくて残念でした。巨人の応援も私の分までお願いしますね。いいお医者さんになってくださいね。ありがとう。”
お姉さんは泣きながら読んでくれました。ご両親も涙をふきながら聞いてくれました。僕もふいてもふいても涙と鼻水が止まらず白衣の袖が重たくなってしまいました。
翌日、僕は約束どおり焼き鳥屋に行きました。生ビールは最初から2杯頼んで、一人でかってに乾杯した後は、飲めないアルコールをわからなくなるまで痛飲しました。
僕は、結局医者として彼女に対し、何の役にも立ちませんでした。それなのに彼女は僕にとても大切なことをたくさん教えてくれました。
あの年、ジャイアンツは結局優勝できませんでした。あれから、もう20年以上の年月が過ぎました。彼女の生きてきた時間をとうに飛び越えて、医師としても折り返し過ぎの時間だと思います。この年になっても彼女が最後にかけてくれた、“いいお医者さん”になれているのかどうかはわかりません。でも、いつかまたどこかの世界で会えたときに胸を張れるよう、“がんばったね”って言ってもらえるような、仕事や生き方をしていきたいと思っています。